コラール・カンタータ300年 実施編(3)
| | | |
 6月15日はいよいよバッハ音楽祭本番当日、今回の旅の最初の山場です。演奏会は15時からですが、直前のゲネプロのため、お昼を済ませて13時には会場のトマス教会へ向かいます。今回はだいたい天気に恵まれ、この日もさわやかな初夏の気候でした。 6月15日はいよいよバッハ音楽祭本番当日、今回の旅の最初の山場です。演奏会は15時からですが、直前のゲネプロのため、お昼を済ませて13時には会場のトマス教会へ向かいます。今回はだいたい天気に恵まれ、この日もさわやかな初夏の気候でした。トマス教会はバッハの最後の職場でもあり、世界中のバッハファン(特に声楽曲ファン)にとっては一度は行きたい聖地です。CDや動画は誰でも入手できるので、バッハの作品を楽しむこと自体は世界中で普通にできるのですが、やはり演奏する側としてこの場所に立ってここの空気を味わえるのはほんの一握り。バッハ音楽祭という晴れの場での演奏機会を二回もいただけて何とも光栄で幸せです。   集まってくる合唱団をまず歌う場所であるオルガン前のバルコニーに誘導して現場での合わせです。オケやソリストとの合わせは前日に済んでいるので、演奏自体には特に不安はありませんでした。 集まってくる合唱団をまず歌う場所であるオルガン前のバルコニーに誘導して現場での合わせです。オケやソリストとの合わせは前日に済んでいるので、演奏自体には特に不安はありませんでした。実際の場所に立ってみて、指揮の見え方や会場の響きを確認し、合唱団の入りの音はどう取るかなど実演の細かい調整をしていきます。声は出しすぎると本番前につぶれる可能性があるのでほどほどに。本番にピークを持って行くのも大事な調整です。 現場合わせが終わったら、これも前日に下見を済ませておいた控室へみんなを連れて行きます。昔の教会の建物なので控えに使える部屋は一つしか無く、できるだけ宿で着替えて集合としましたが完全に本番姿のまま街を歩くのも荷物もあり大変なので、時間差での着替えなども指示しました。 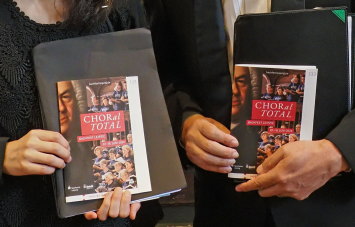 モテッテ演奏会は、音楽祭のプログラムの一つではありますが、他の演奏会とは少し違って礼拝の形を取ります。もともとはトマス教会合唱団が担当する礼拝枠をこの日は私達が引き受けるということになります。午後に行うモテッテは晩課といわれ、午前の礼拝枠のメッテ(朝課)と合わせて音楽祭期間中に何回か組まれていました。 モテッテ演奏会は、音楽祭のプログラムの一つではありますが、他の演奏会とは少し違って礼拝の形を取ります。もともとはトマス教会合唱団が担当する礼拝枠をこの日は私達が引き受けるということになります。午後に行うモテッテは晩課といわれ、午前の礼拝枠のメッテ(朝課)と合わせて音楽祭期間中に何回か組まれていました。演奏会を聞きにやってくる外の人向けではなく、基本的には教区の人達のためのものなので、入場料が100ユーロを超えることも珍しくない他のプログラムに比べ、3ユーロと破格です。そのためメッテもモテッテも大人気で、普通の市民が大挙して押しかけるそうです。前売りもしないので、聞きたいと思えば並んで当日券を買うしかありません。3ユーロというのは、他の演奏会でいうとプログラム冊子(写真左)の代金で、モテッテは冊子を買ってそれを見せて会場に入るということになっていました。冊子がチケットの代わりです。やはり開演時間のかなり前から、外のチケット(冊子)売り場には長蛇の列ができていたそうです。 合唱団には関係者用にプログラム冊子が30部割り当てられ、友人知人や家族に事前に渡しておけば当日並ばなくても入れるというサービスをしてくれていて、欲しい人には前日の見学会の時にTシャツと一緒に配っておきました。今回は、事前の準備や合唱団のための配慮をいろいろしてくれて有難かったのですが、間に入ってそれを合唱団に届ける事務局としては仕事が増えて結構大変でした。  ゲネプロが終わったら一旦教会は閉められ、リハーサルを聞いていた観光客も追い出されていなくなりました。演奏会に向けての準備が万端整うと、いよいよモテッテ本番となります。 ゲネプロが終わったら一旦教会は閉められ、リハーサルを聞いていた観光客も追い出されていなくなりました。演奏会に向けての準備が万端整うと、いよいよモテッテ本番となります。控室で簡単にストレッチと発声をしたあと、普通に二階客席を通ってさっきのバルコニーに何となく向かいます。普通の演奏会のように客席が暗くなって合唱団は整列してステージに入場ということはなく、教会での演奏会はいつもゆるい始まりになります。そのあとオケも何となく集まってくる感じ。  バルコニーから見る教会の景色は、基本的には300年前とあまり変わっていません。照明がロウソクから電気になり、オルガンの配置も変わって、バッハやメンデルスゾーンのステンドグラスがはまったりしていますが、建物自体は昔からのものがそのままです。 バルコニーから見る教会の景色は、基本的には300年前とあまり変わっていません。照明がロウソクから電気になり、オルガンの配置も変わって、バッハやメンデルスゾーンのステンドグラスがはまったりしていますが、建物自体は昔からのものがそのままです。樋口先生の立つ指揮台の場所に、300年前に実際にバッハが立っていたのだと思うと感無量です。1724年の6月は、いろいろ他のページでも書いた通りライプツィヒ二年目のコラール・カンタータ年巻が始まったばかりで、幕開けとなったBWV20が6月11日に初演された直後という状況になります。 さらにその100年前の1624年は、始まったばかりの三十年戦争もまだ直接の被害が出ていなかった頃で、その前年に名作「イスラエルの泉」を発表したばかりのヨハン・ヘルマン・シャインがカントルとして同じこの場所に立っていました。 私達のいるバルコニーも、上で書いた通り普段はトマス合唱団が歌っている場所で、300年前の当時トマス学校にいたヨハン・ルートヴィヒ・クレープスやヨハン・クリストフ・アルトニコルやゴットフリート・アウグスト・ホミリウスといったバッハの高弟(それぞれ時期は違いますが)も、この場に立って歌ったりオーケストラのヘルプや副指揮で駆り出されていたかも知れません。前日の見学会で見た楽譜の筆写者アンドレアス・クーナウ(前任カントルの甥)も、たぶんここにいたことでしょう。1724年には14歳だったフリーデマンや10歳だったエマヌエルも、変声直前のボーイソプラノで参加していたに違いありません。などなど、これまであれこれと本で読んだり見聞きしたことが頭の中に次から次へと蘇ってきて、ひとしきり当時に思いを馳せていました。  上の写真は開場直後ですが、すでに身廊中央はほぼ満席、二階席も埋まり始めています。開演までには側廊も埋まってぎっしり満席となった聴衆を前に、主催者の挨拶でモテッテは定刻に始まりました。トマス教会オルガニストのヨハネス・ラング氏の素晴らしいコラール前奏曲のあと、シュッツから私達の歌が始まります。シェーンベルクまで歌ったあとは聖書の朗読と会衆のコラール斉唱、祈りと祝福と続き、メインのカンタータBWV68を歌って、お開きとなりました。 上の写真は開場直後ですが、すでに身廊中央はほぼ満席、二階席も埋まり始めています。開演までには側廊も埋まってぎっしり満席となった聴衆を前に、主催者の挨拶でモテッテは定刻に始まりました。トマス教会オルガニストのヨハネス・ラング氏の素晴らしいコラール前奏曲のあと、シュッツから私達の歌が始まります。シェーンベルクまで歌ったあとは聖書の朗読と会衆のコラール斉唱、祈りと祝福と続き、メインのカンタータBWV68を歌って、お開きとなりました。やはり本場の響きは格別で、音程など不思議といい方(現場で美しく響く方)に変わっていきいます。いつも会議室で練習しているときとは別の合唱団のようでした。気持ちよく歌いきることができ、メンバーも大感激です。教会音楽は教会で歌ってこそ、という当たり前のことを今更ながらに実感しました。 樋口先生の旧友で音楽祭総監督のミヒャエル・マウルさんも終演後にご挨拶に見えました。  打上は、前回同様アウエルバッハス・ケラーにしました。先生はもとより皆さんご機嫌で、こちらも大変でしたが報われた気がしました。結構飲み過ぎた人も多かったですが、翌日はヴルツェンでの礼拝参加、朝早い集合となります。 打上は、前回同様アウエルバッハス・ケラーにしました。先生はもとより皆さんご機嫌で、こちらも大変でしたが報われた気がしました。結構飲み過ぎた人も多かったですが、翌日はヴルツェンでの礼拝参加、朝早い集合となります。 |
| 最終更新 2024. 8.25 |
Copyright © 2000 Bachhaus Kawaguchi All rights reserved.